どうも、じょりじょりです。
「ラケットは決まったけど、ストリング選びで迷っている」「複数ラケットを使ってみたけど“しっくりくる”組み合わせがない」――そんなあなたのために、僕がこれまで 300本以上のラケット・ストリングを試してきた経験も踏まえつつ、
「自分に合うセッティング」を見つけるための考えを紹介します。
(筆者のレベルもそこまで高くないのであくまで一つのアプローチとして参考にしてください)
目次
- セッティング選びでまず意識すべき“妥協”
- “譲れない要素”を決める
- ラケット × ストリングの組み立て方
- 実戦を通じた検証と選定プロセス
- ラケットを頻繁に変えない理由
- 注意したい落とし穴・誤解
- 結び:セッティングは“旅”である
1. セッティング選びでまず意識すべき“妥協”
セッティングを探すとき、多くの方が「全部良いものを求めたい」と思いがちです。
しかし、完璧な組み合わせを追求しすぎると、選択肢が無限に広がり、迷宮入りすることになりがちです。
妥協は必須である
私自身、過去には「打感」「反発」「コントロール」「見た目」「重量バランス」…など多くを求めすぎて、選定に疲弊した経験があります。市販ラケットには個体差もありますから、
思いどおりにいかないこともかなりあります。
だからこそ、「妥協できる点」をあらかじめ決めておくことが重要です。
すべてを満たすものなどほぼ存在しませんので、最初から「ここは妥協する」と線引きしておけば、決断しやすくなります。
たとえば、私の場合は次の2点を妥協対象にしています。
- 打感(特に“柔らかさ・硬さ”の絶妙な微調整までは追わない)
- カラー・デザイン(見た目はある程度受け入れられるものならよし)
このように、妥協対象は多すぎても少なすぎても選択が難しくなるので、「2〜3点」程度に留めておくのが現実的です。
2. “譲れない要素”を決める:あなたの基準を持つ
妥協を持つ一方で、絶対に譲れない要素も定めておくことが大切です。私の場合、譲れないのは以下の 2点です。
- ボールの軌道
自分が描く理想的な弾道があるなら、それに近づけられるセッティングを選びたい。軌道がイメージと大きく違うと、修正に意識をとられてミスが出やすくなるからです。 - 勝率(結果)
見た目や感覚より、実際の試合や練習試合で「勝てるかどうか」が最終判断基準。実践での勝率が高いセッティングを優先します。
“譲れない要素”は人によって異なります。例えば、
- コントロール性
- スピンのかかり
- 手首・肘への負担軽減
- 打球の飛び
- 自己が感じる“安心感”
など、自分にとって最も重要な “非妥協項目” を 1〜2 個決めておくとよいでしょう。
3. ラケット × ストリングの組み立て方:思考ステップ
譲れない点、妥協点を決めたうえで、ラケットとストリングの組み立てを進めます。
ステップ A:軌道のイメージでラケットを選ぶ
最初に、“ボールが上がる・弾道が出る感覚” を重視して、複数モデルの試打をして比較することを推奨します。
自分が想像する軌道に近いものを軸に据え、それに合うストリングを選ぶアプローチです。
ただし、ラケットは容易に頻繁に変えない方がよいので、多少感覚とズレても「調整次第でどうにかなるか?」と考えられるラケットを選ぶのがコツです。
ステップ B:ストリングで軌道を微調整
ラケットをある程度絞ったら、ストリングを複数張って試し、軌道に近づけるように調整していきます。以下のポイントが有効です。
- ストリングの素材違い(ポリエステル(多角形、丸型)、ナイロン系、ナチュラル、ハイブリッドなど)を試す
- 張力(テンション)の上下調整
- 縦糸 vs 横糸の組み合わせ(ハイブリッド張り)
上述のような調整を通じて、思い描く弾道に近づけられそうな組み合わせをピックアップします。
ステップ C:感覚と客観、双方で評価
調整した各組み合わせについて、次のような観点で評価を行います。
| 評価視点 | 内容 |
|---|---|
| 主観的な感覚 | 打球感、弾き、衝撃の少なさ、球離れの印象 など |
| 客観的な実績 | 練習試合での勝率、相手の意見など |
私の場合、「主観 2 割、客観 8 割」で判断することが多いです。つまり、感覚的に“良い感じ”という理由だけで決めるのではなく、
実際の試合での感覚・結果を重視します。
また、異なるプレースタイルの相手(ボレー得意、シコラー、パワーヒッターなど)複数人から感想をもらい、そのセッティングで勝てるかどうかを試すのも有効です。
ステップ D:最終決定
複数組み合わせを試したら、自分の“譲れない要素”に最も近づくものを最終候補とし、1 種類に絞ってしばらく使うようにします。
ただし、「最初に感じた良さ」が様々な要因で時間とともに変わってくることもあります。
そのため、3 か月〜1 年程度使ってから、自分とラケット・ストリングに馴染みが出てから再評価するのがオススメです。
4. 実戦を通じた検証
最終的には自分の実戦での感覚と結果で判断しています。
- 複数セッティングをテスト
例:A セッティング(ポリ系、50ポンド)、B セッティング(ハイブリッド、48ポンド)など。 - 練習試合/本番形式で比較
できるだけ同じコンディションで、そして異なるタイプの相手とも試す。 - 相手・観戦者のフィードバックを収集
返球感・球の質について、相手から「重い」「伸びる」「前のラケットの方が良かった」など意見をもらう。 - 勝率・ミス傾向を記録
それぞれのセッティングで、ミスの出やすいショット(ストレート、クロス、リターンなど)をメモする。エクセルやノートにまとめておくとかなり楽です。 - フィードバック
どのショットをミスした。得点したなど記録しておいて自分で分析できる方は自分で分析しましょう。細かい解析ができない筆者はAIに頼ります笑。
筆者はレベルはそこまで高くありません。そのレベルでここまで行う必要があるのかという意見もあると思います。
しかし最近はラケットも高く筆者も損はしたくないので、行います。
レベルは個々で違えどここまでしっかり行えば、ラケット選択ミスはかなり減ると思います。
5は時間なければ大丈夫です。4まで行うだけでも全然違います。
5. ラケットを頻繁に変えない理由
多くのプレーヤーは「次はあのモデルを使ってみたい!」と気になるものですが、私は、ラケットは少なくとも 1 年は使うべきだと考えています。
その理由は以下の通りです:
- 慣れと適応期間
新しいラケットを使い始めてすぐは良く感じられても、2〜3 か月経つとスイングが馴染んできて、今まで見えていなかったズレが表面化することが多い。 - 判断基準のブレを防ぐ
頻繁に変えると、「本当にラケットが悪いのか? 自分の調子が悪いのか?」の判断がつきにくくなる。 - コストと手間
頻繁な買い替え・セッティング調整はコストがかかるうえ、微調整が追いつかなくなります。 - “パートナー感”の構築
僕は概念も大事にしています。長く使ってラケットを信頼できれば、いざという場面で安心して振れます。
新しいラケットを使いたい気持ちはわかりますが、一定期間使い込んでから判断できるようにする方がオススメです。
6. 注意したい落とし穴・誤解
セッティング探しの過程で、以下のような落とし穴や誤解に引っかかることがあります。意識して避けましょう。
- “打感の良さ=正解”と思い込みすぎる
快適な打感だからと言って実戦での安定性や勝率に繋がるわけではありません。 - 極端なスペックの追求
張力を高すぎ/低すぎにする、素材を過度に硬い/柔らかいものにするなどは、暴発などで感覚が狂うことがあります。 - 張り替えタイミング・テンション低下を無視する
ストリングは時間と使い込みでテンションが落ち、性能が変化します。特にポリによっては性能変化が顕著です。適度な張替えは行いましょう - 情報バイアス
ストリング・ラケットのインプレ記事は筆者の主観や好みに左右されがちです。複数ソースを比較し、バイアスを除く視点を持ちましょう。
7. 結び:セッティングは“旅”である
アマチュアにとってラケット × ストリングのセッティング選びは、終着点がない「探求の旅」のようなものです。
でもテニスはセッティング選びが楽しいところでもあります。
ゴルフも似たようなところありますね。
筆者の1意見ですが、以下の点を心掛けながらセッティング選びを行うと楽しいです。
- 妥協点を意識しつつ、譲れない要素を明確に持つ
- 一定期間は絶対に使う
- 変えたい欲求に流されすぎないようにする
- 他者の意見・感覚も大切にするが、最終判断は自分で
それではここまで読んで頂きありがとうございました。

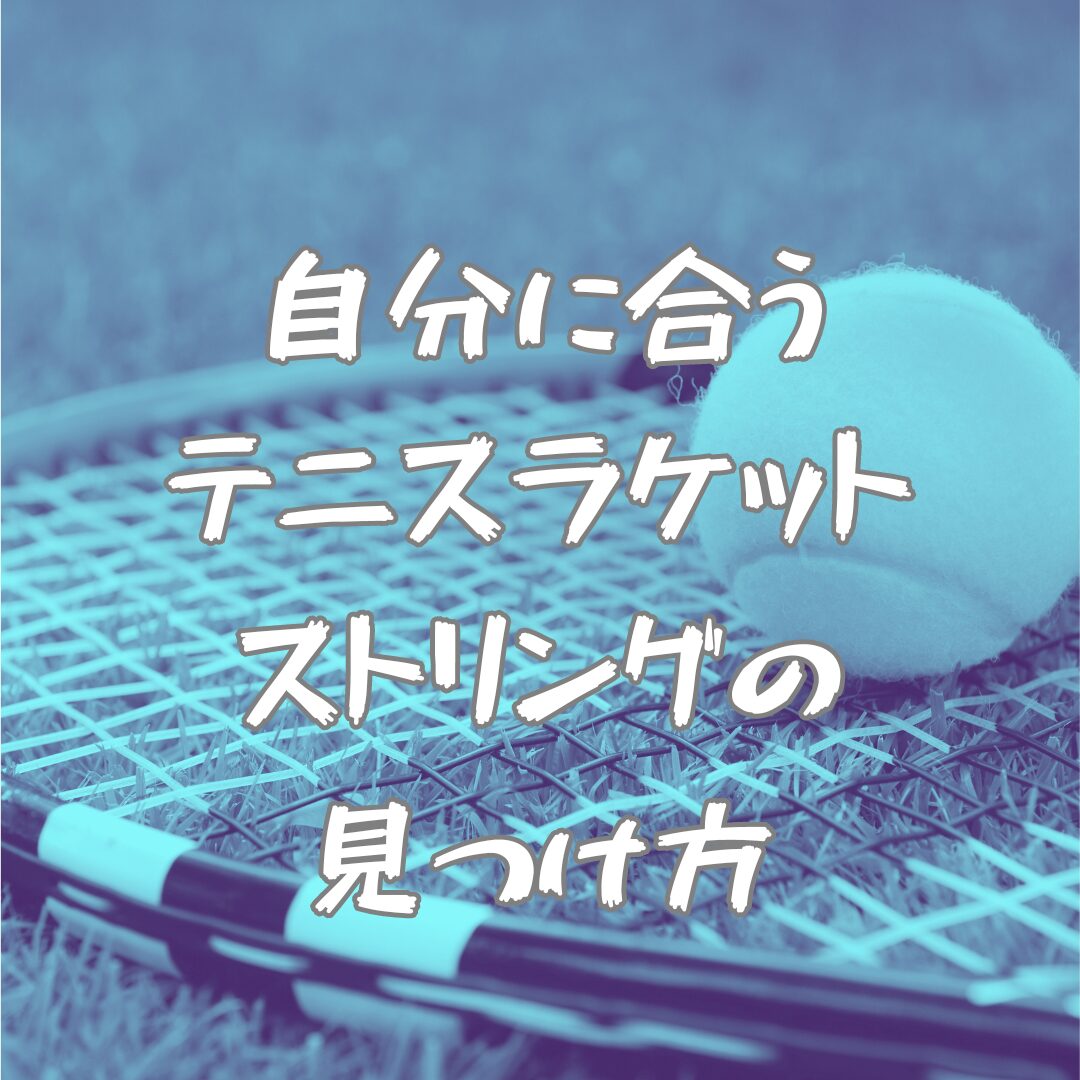
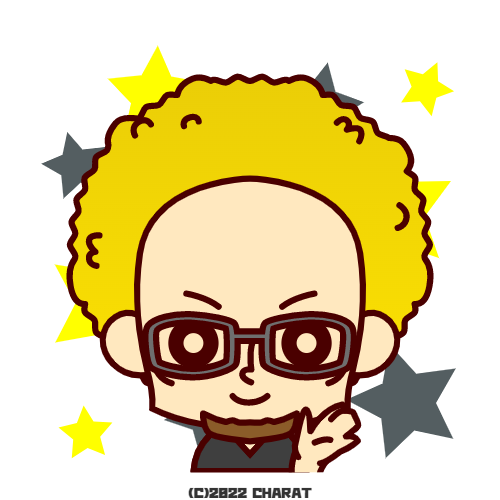
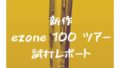
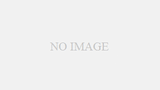
コメント